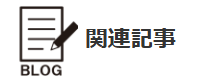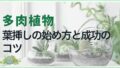- 1家庭菜園に適した土の性質や種類
- 2
野菜が育ちやすい土のpHや栄養バランス - 3土作りや肥料・堆肥・石灰の使い方
- 4土の再利用や連作障害、虫対策の方法
家庭菜園の土が野菜の成長を決める理由

- 家庭菜園に適した土は?
- 野菜がよく育つ土は?
- 家庭菜園 土 種類の選び方
- 家庭菜園 土 pHの重要性
- 家庭菜園 土 水はけ改善のコツ
- 家庭菜園 土 虫対策で大切なこと
家庭菜園に適した土は?
家庭菜園に適した土は、水はけと保水性のバランスが良く、栄養分が豊富な土です。これが整っていることで、野菜が元気に成長します。
なぜなら、水はけが良すぎると土が乾燥してしまい、植物が必要な水分を十分に吸収できません。一方で、水もちが良すぎる粘土質の土は、根腐れを引き起こす可能性が高くなります。つまり、適度な水分を保持しつつ、余分な水分をすぐに排出できる土が理想的ということになります。
具体的には、「壌土(じょうど)」という、砂質と粘土質の中間的な性質をもつ土が家庭菜園に適しています。壌土は、空気をしっかり含むため通気性も良好であり、根が張りやすいという利点があります。さらに、有機物が多く含まれていることも重要です。腐葉土や堆肥を混ぜ込むことで、土中の微生物が活発になり、団粒構造という小さな土の塊が形成されます。この団粒構造があることで、水や栄養分を効率よく植物に供給することが可能になるのです。
ただ、家庭菜園の規模や育てる植物の種類によっては、これらの条件を整えるのが難しい場合もあります。たとえば、ベランダのプランター栽培であれば、ホームセンターで販売されている専用の培養土を購入し、自宅で手軽に使うという方法もおすすめです。
いずれにしても、自分の育てる野菜の種類に応じて、土壌の状態を見極め、適切な配合で調整することが、家庭菜園を成功させる大切なポイントになります。
野菜がよく育つ土は?
野菜がよく育つ土とは、適度なpH(酸度)と栄養バランスが整った土です。土壌が適切な状態になっていると、野菜の生育がスムーズになり、病気や害虫にも強くなります。
まず、土のpHが大きな役割を果たします。野菜の種類ごとに適切なpHがあり、一般的には弱酸性~中性(pH6.0〜7.0)が理想的な範囲です。例えば、トマトやキュウリ、ニンジンはpH5.5~6.5、ホウレンソウはpH6.5~7.0の範囲が好ましいとされています。このため、育てたい野菜の種類に合わせて、苦土石灰などの石灰質肥料を使い、酸性に傾いた土を中和する必要があります。逆に、土がアルカリ性に傾き過ぎている場合は、ピートモスなどを混ぜることで酸性に戻すことができます。
また、土の栄養バランスも重要な要素です。野菜の成長には、主に窒素・リン酸・カリウムという三大栄養素が必要です。窒素は葉や茎の成長を促し、リン酸は花や実の形成を助け、カリウムは根の発育や病害抵抗性を高めます。具体的には、有機肥料として鶏ふんや油かす、化成肥料として複合肥料などを適量使い分けると良いでしょう。ただし、肥料の与え過ぎは「肥料焼け」を起こし、かえって野菜を弱らせてしまいます。だからこそ、肥料の量や頻度には細心の注意が必要です。
さらに、野菜が元気に育つ土には、多様な微生物が存在しています。微生物は土壌中の有機物を分解し、野菜が吸収しやすい養分に変えてくれるためです。微生物を増やすためには、堆肥や腐葉土を定期的に土に混ぜ込むことが有効です。
このように、野菜がよく育つ土を作るには、pH調整、栄養素のバランス管理、微生物の活性化という三点を総合的に考えることが求められます。自分の育てる野菜に合わせて、適切な方法で土づくりを行うことが、収穫成功への近道となります。
家庭菜園 土 種類の選び方
家庭菜園の土は、野菜を健康に育てるための基盤となります。どのような土を選ぶかによって、生育の良さや病害虫の発生率まで大きく変わります。そのため、目的に合った土の種類を選ぶことが重要です。
まず、家庭菜園の土の種類として大きく分けると、「培養土(ばいようど)」「腐葉土(ふようど)」「赤玉土(あかだまつち)」などが挙げられます。培養土はホームセンターなどで手軽に購入できるもので、野菜の栽培に必要な肥料や養分があらかじめ配合されています。初心者が家庭菜園を始める場合には、迷わず培養土を選ぶのがよいでしょう。ただ、培養土は一定期間で養分が切れるため、定期的な追肥が必要になります。
次に、腐葉土は、落ち葉や枯れ枝が微生物の力で分解された土です。腐葉土を土に混ぜることで土壌の通気性や保水性が改善され、野菜の根が張りやすくなります。また、有機物を多く含むため、微生物が活発になり土壌を健康に保つ効果もあります。ただし、腐葉土単体では肥料成分が少ないため、肥料を追加で与えることが必要です。
一方、赤玉土は粒状の粘土質の土で、保水性が高く植物の根に酸素を供給しやすいという特徴があります。特にプランター栽培では、赤玉土をベースに培養土や腐葉土を混ぜて配合すると、水はけが良くなり過湿を防ぐことができます。ただし、赤玉土は時間が経つと崩れて排水性が落ちるので、長期間使用する場合は定期的な入れ替えや追加が必要になります。
こう考えると、選ぶ土の種類によって、それぞれ一長一短があることがわかります。自宅の庭であれば、既存の土に腐葉土や堆肥を加えた土作りをするのが経済的ですが、ベランダや限られたスペースでの栽培であれば、手間がかからない培養土を購入するのがおすすめです。育てる野菜の種類や栽培環境に応じて最適な土を選択し、自分だけの家庭菜園を楽しみましょう。
家庭菜園 土 pHの重要性
 家庭菜園を成功させるには、土のpH管理がとても重要です。土壌のpH(酸度)が適正でないと、野菜が本来持つ成長力を十分に発揮できず、収穫量や品質が低下してしまうからです。
家庭菜園を成功させるには、土のpH管理がとても重要です。土壌のpH(酸度)が適正でないと、野菜が本来持つ成長力を十分に発揮できず、収穫量や品質が低下してしまうからです。
まず、pHとは土壌の酸性度やアルカリ性度を示す数値で、一般的にはpH7.0を中性として、それより数値が低いと酸性、高いとアルカリ性を示します。多くの野菜はpH6.0~7.0の弱酸性~中性を好むため、この範囲内で土壌を調整する必要があります。例えば、ホウレンソウやキャベツはややアルカリ寄りのpH6.5〜7.0、ジャガイモやトウモロコシは酸性寄りのpH5.5〜6.0が適しています。
それでは、土壌のpHが適切でないと何が問題になるのでしょうか。土壌が酸性に偏りすぎると、野菜が栄養分を十分に吸収できず、生育不良や病害虫の発生を招きやすくなります。一方で、土壌がアルカリ性に傾き過ぎると、鉄分やマグネシウムなどの微量栄養素が吸収されにくくなり、葉が黄色くなる「クロロシス」と呼ばれる症状が現れることがあります。
これを防ぐには、土の状態を把握して調整することが大切です。具体的には、ホームセンターで購入できるpH測定キットや試験紙を使い、自宅の土壌が酸性かアルカリ性かを確認します。酸性に偏っている場合は苦土石灰(くどせっかい)や消石灰(しょうせっかい)を適量混ぜ込むことで、中和できます。ただし、石灰を施したらすぐに土壌としっかり混ぜ合わせる必要があります。雨で固まってしまうと、逆に土壌環境を悪化させることになりかねません。一方、アルカリ性になった土壌は、ピートモスや鹿沼土(かぬまつち)を混ぜ込むことで、徐々に酸性方向へ調整できます。
また、長期的に見ると、肥料の使い方によって土壌のpHは変動していきます。特に鶏ふんなどのアルカリ性肥料を継続的に使うと、土壌が次第にアルカリ性に傾いてしまうこともあるため注意が必要です。このように、土壌pHを定期的に確認し調整を続けることで、家庭菜園の野菜が元気よく育ち、おいしく豊かな収穫を楽しむことができるでしょう。
家庭菜園 土 水はけ改善のコツ
家庭菜園で野菜を健康に育てるには、土の水はけを改善することが非常に重要です。水はけが悪い土は、根腐れを起こしたり、病気が発生しやすくなったりするため、早めに対策を行うことをおすすめします。
水はけの悪い土の原因は、主に粘土質であったり、土が踏み固められたりしていることにあります。これを改善するためには、「土壌改良材」を利用するのが最も手軽で効果的です。例えば、腐葉土や堆肥を加えることで土の中に団粒構造という隙間ができ、空気が入りやすくなり、自然と水の流れも良くなります。また、砂やパーライトを混ぜると、土壌の密度が低下して通気性と排水性が大幅に向上します。
他の方法としては、「高畝(たかうね)」を作ることも有効です。畝とは野菜を植える土を盛り上げた部分のことで、この高さを20cm程度にすると、雨が降っても水が停滞せず、速やかに流れます。特に大雨が降った後でも根の周囲が水浸しにならず、植物が健康な根を張りやすい環境を整えられます。
なお、水はけを改善するときに注意すべきなのは、単純に砂を多量に混ぜるだけでは逆効果になることもある点です。砂を入れ過ぎると、逆に水もちが悪くなり、頻繁に水やりが必要になるデメリットがあります。そのため、腐葉土や堆肥など保水性を適度に持つ資材を一緒に混ぜることが大切です。
こうして適切な土壌改善を行えば、水はけの良い理想的な環境が整い、野菜が丈夫に育ちやすくなります。まずは自分の庭やプランターの土の状態をよく観察し、必要な改善方法を試してみると良いでしょう。
家庭菜園 土 虫対策で大切なこと
家庭菜園を楽しんでいると、多くの方が直面する問題が虫害です。特に土壌に潜む害虫は野菜の根や茎を傷つけ、生育を妨げます。そのため、事前に虫対策をしっかりと行うことが大切です。
土壌の虫対策として一番重要なことは、「健康で清潔な土壌環境」を維持することです。例えば、土の中には、ネキリムシやコガネムシの幼虫といった根を食べる害虫が潜んでいることがあります。これらの虫は、有機物の未分解な状態や湿り過ぎた環境を好むため、未熟な堆肥の使用や水分管理の不徹底が問題を引き起こします。したがって、堆肥を使う際は必ず完熟したものを選び、水やりの頻度を見直して、土壌が過湿にならないように注意する必要があります。
また、輪作(連作を避けるために異なる科の植物を順番に植えること)も虫害対策として有効です。毎年同じ場所で同じ野菜を栽培すると、特定の害虫が増えやすくなるため、数年ごとに異なる種類の作物を育てることで、害虫が定着しにくい土壌環境を作ることができます。
一方で、農薬を使いたくない方には、「天然素材を利用した防除法」もおすすめです。例えば、木酢液(もくさくえき)やニームオイルなどは害虫の忌避効果が高く、環境にも優しい方法です。ただし、これらも適切な量やタイミングで使用しないと、植物自体に悪影響を及ぼすことがあるため、パッケージに記載されている使用方法を守ることが大切です。
他にも、定期的に土を掘り起こし、日光に晒して土を乾燥・殺菌する方法も効果的です。特にプランター栽培の場合は、土壌を再利用する際にこの方法を取るとよいでしょう。
このように、虫害対策は事前の予防策が何より重要です。常に土の状態を確認し、適切な管理を継続することが、家庭菜園を長く快適に楽しむための秘訣になります。
家庭菜園の土作りを成功させる方法とポイント

- 家庭菜園 土 作り方の基本手順
- 家庭菜園 土 肥料の種類と施し方
- 家庭菜園 土 堆肥の上手な使い方
- 家庭菜園 土 石灰の使い方と注意点
- 家庭菜園 土 連作障害を防ぐ方法
- 家庭菜園 土 再利用のポイントと注意点
- 家庭菜園 土 作りで押さえるべきポイントまとめ
家庭菜園 土 作り方の基本手順
家庭菜園を成功させるには、土づくりの基本手順を理解することが重要です。良い土ができれば、野菜が健康に育ち、収穫量も安定します。
まずは、土壌の状態をチェックするところから始めましょう。具体的には、スコップや手を使って土を掘り起こし、土の感触を確認します。指で軽く押して簡単に崩れるようであれば、柔らかく適度な状態といえますが、固く締まっている場合は土壌改良が必要になります。固い土は野菜の根が張りにくく、水はけも悪いため、植物がうまく育ちません。
次に、土壌を改良するために腐葉土や堆肥を加えます。一般的な目安としては、1㎡あたり腐葉土を2~3kg、堆肥を3~4kg程度混ぜるのが適切です。これを土にまんべんなく撒いた後、スコップやクワで20〜30cmの深さまでしっかり耕し、均一に混ぜ込みます。この際、石やゴミ、大きな土の塊は取り除き、根が伸びやすいように細かな状態に仕上げることがポイントです。
土壌改良が終わったら、土の酸度(pH)を調整します。多くの野菜は弱酸性~中性(pH6.0~7.0)を好みますので、酸性土壌の場合は苦土石灰や消石灰を散布して調整しましょう。アルカリ性土壌の場合はピートモスを混ぜることで酸度を下げることができます。ホームセンターなどで手に入る簡単なpH測定キットを使えば、自宅でも手軽に酸度チェックが可能です。
また、植え付け前には土壌をよく馴染ませるために、最低でも2週間は寝かせる期間を設けましょう。これにより、肥料や石灰などが土壌と馴染み、有機物が適切に分解され、微生物の活動も活発になります。ただ、この期間を設けずに植え付けてしまうと、肥料や石灰の影響で苗が根焼けを起こす危険性があります。
これらの手順を丁寧に行えば、理想的な土壌環境が整います。初心者でも、手順通りに進めることで失敗を防ぐことが可能です。土作りをしっかり行って、元気な野菜を育てましょう。
農林水産省の「土づくり技術対策指針」では、土壌改良や肥料の施用方法について詳しく解説されています。
家庭菜園 土 肥料の種類と施し方
家庭菜園で元気な野菜を育てるためには、土壌への肥料の施し方を理解することが大切です。肥料の種類や施し方が適切であれば、野菜が必要な栄養素を効率よく吸収できるようになります。
まず肥料の種類について、家庭菜園では大きく分けて「有機肥料」と「化成肥料」の2つがよく使われます。有機肥料には、鶏ふんや牛ふん堆肥、油かす、骨粉などがあり、土壌中の微生物によって徐々に分解されるため、効果がゆっくり現れ長持ちします。ただし、即効性がないため、生育期間が短い作物やすぐに栄養を補給したい場合には不向きです。一方、化成肥料は化学的に製造された肥料で、栄養素が明確に示されており、すぐに効果が出るのが特徴です。即効性があるので追肥として使いやすく、特に初心者でも管理が簡単です。
次に施肥のタイミングと施し方ですが、肥料には大きく分けて「元肥(もとごえ)」と「追肥(ついひ)」があります。元肥とは苗を植える前に土に施しておく肥料のことで、植物が成長する基盤を整える役割を果たします。具体的には、堆肥や緩効性の有機肥料を土とよく混ぜて使うのが一般的です。例えば、1㎡あたり鶏ふん堆肥を1~2kgほど入れ、深く耕して均一に混ぜ込んでおきます。
一方、追肥は植物が生育途中に追加で与える肥料です。野菜が成長するにつれて栄養を使い果たしてしまうため、追肥で適度に補充することが必要になります。一般的には、生育が旺盛な葉物野菜や実をつける果菜類には2~3週間に一度、速効性のある化成肥料や液体肥料を使うと効果的です。ただし、肥料の量が多すぎると「肥料焼け」を起こし、根が傷むことがあります。パッケージの表示に従った適切な使用量を守りましょう。
また、肥料を施す場所もポイントです。追肥の場合は、株元から少し離れた場所に溝を作り、そこに肥料を入れて土で軽く覆います。こうすることで肥料が根に直接触れて根焼けを起こすリスクを避けられます。
このように、肥料の種類や施し方を正しく理解し、目的や野菜の種類に応じて使い分ければ、家庭菜園の野菜はより健康に育ちます。初心者の方も、焦らずゆっくりと学びながら施肥のコツを掴んでいくことをおすすめします。
家庭菜園 土 堆肥の上手な使い方
家庭菜園で野菜を元気に育てるには、堆肥の正しい使い方がとても重要です。堆肥は、土壌に栄養を補給するだけでなく、土の質を改善し、微生物を活発にする役割があります。ただ、使い方を間違えると、かえって野菜が育ちにくくなってしまうので注意しましょう。
まず堆肥を選ぶ際には、「完熟した堆肥」を選ぶことがポイントです。堆肥には、牛ふん堆肥、鶏ふん堆肥、腐葉土堆肥など、さまざまな種類があります。これらは分解の進み具合が異なり、未熟な堆肥を使うと土中で分解が進み、窒素飢餓(窒素が不足して植物が育ちにくくなる現象)を引き起こします。そのため、ホームセンターなどで購入する際には、完熟と表示されている堆肥を選ぶのが安心です。
堆肥を使うタイミングも大切です。種まきや苗を植える約1か月前に、土に堆肥を混ぜ込んでおくとよいでしょう。例えば、1平方メートルあたり2~3kgほどを目安にして、20~30cmほどの深さまでしっかり耕して土と混ぜます。これにより堆肥が土になじみ、有機物がゆっくりと分解され、微生物が活発に活動しやすい環境が整います。こうすることで、野菜が植えられた後も栄養を長期間にわたり供給できるようになります。
また、野菜の種類によっても堆肥の量を調整すると良いでしょう。ナスやトマトなどの収穫量が多く、長期間育てる野菜の場合、土壌から養分をたくさん吸収します。そのため、通常より多めに堆肥を入れておくのがおすすめです。一方、収穫期間の短い葉物野菜などは、過剰に堆肥を使うと逆に栄養過多になるため、控えめにすると適切です。
このように、堆肥を上手に利用することで土壌が豊かになり、野菜の育成が安定します。ただ単に堆肥を多く入れればよいのではなく、野菜の種類や育てる期間に応じて量やタイミングを工夫することが、家庭菜園を成功させるコツです。
家庭菜園 土 石灰の使い方と注意点
家庭菜園を始める際に意外と見落とされがちなのが、石灰の使い方です。石灰は、土壌の酸性度(pH)を調整し、野菜が育ちやすい環境を作る重要な資材です。ただし、正しく使わないと野菜の生育に悪影響を及ぼすこともあるため、使い方には注意が必要です。
一般的に家庭菜園で使われる石灰は、「苦土石灰(くどせっかい)」と「消石灰(しょうせっかい)」の2種類です。苦土石灰はマグネシウムを含んでいるため、植物の葉緑素の生成を助ける効果があります。一方、消石灰はアルカリ性が強く、土壌の酸度調整効果が速く現れる特徴があります。初心者の方には、比較的扱いやすく、緩やかに酸度調整ができる苦土石灰がおすすめです。
石灰を使うタイミングは、苗や種を植える2~3週間前が理想的です。使用する量の目安としては、土壌を10cmの深さで耕した場合、1平方メートルあたり苦土石灰なら約100~150g程度、消石灰の場合は約80~100g程度が適切です。これを土の表面に均一に撒き、スコップやクワでよく混ぜ合わせます。この際、土としっかり混ぜ込まないと、石灰が雨で固まってしまい、逆に水はけが悪くなることもあるため注意が必要です。
石灰を使う際に特に気をつけたいのは、施す量を守ることです。適切な量より多く使うと土壌が過度にアルカリ性になり、微量栄養素(鉄やマンガンなど)が吸収されにくくなることで、植物が栄養不足を起こします。また、石灰と肥料を同時に施すことも避けましょう。石灰と肥料を一緒に混ぜると、化学反応を起こしてアンモニアガスが発生し、苗の根を傷める原因になります。そのため、石灰と肥料は最低でも1~2週間の間隔を空けて使用するのが良い方法です。
家庭菜園を楽しむ上で、石灰の使い方をしっかり理解すれば、土壌環境が整い、野菜の健康的な成長をサポートできます。土の酸度調整を定期的に行い、安定した収穫を目指しましょう。
家庭菜園 土 連作障害を防ぐ方法
家庭菜園を続けていると、同じ場所で毎年同じ野菜を育てることが多くなりますが、これは連作障害を引き起こす原因になるため注意が必要です。連作障害とは、同じ種類や同じ科の植物を連続して栽培することで土壌の特定の養分が減少し、害虫や病気が発生しやすくなる現象です。連作障害が起きると野菜が育ちにくくなり、収穫量や品質の低下につながります。
これを防ぐためには、まず「輪作」を取り入れることが効果的です。輪作とは、異なる科の野菜を順番に栽培する方法で、特定の養分が偏って消耗されることを防ぎます。例えば、ナス科のトマトやナスを栽培した翌年は、マメ科のインゲンやエンドウ豆、あるいはアブラナ科のキャベツや小松菜などを栽培するのがよいでしょう。マメ科の植物は根に共生する微生物によって空気中の窒素を土壌に供給してくれるため、土壌改善効果も期待できます。
また、連作障害を避けるためには土壌の消毒や改良も有効です。具体的な方法として、土壌を掘り起こして日光に当てる「太陽熱消毒」があります。夏の暑い時期に土を深さ30cmほど掘り返し、ビニールシートを被せて1~2週間ほど放置すると、熱で病害虫や雑草の種子を減らすことができます。ただし、この方法は狭いスペースやプランターでは手間がかかるため、小規模な場合は市販の土壌消毒剤や微生物資材を使用するのもよいでしょう。
さらに、堆肥や腐葉土などの有機物を土壌に定期的に混ぜ込むことで、土の中の微生物を活性化し、土壌環境を健全に保つ効果があります。ただし、有機物は必ず完熟したものを使用しましょう。未熟な堆肥は逆に窒素不足を引き起こし、野菜が育ちにくくなることがあります。
家庭菜園を楽しむためには、土壌管理が重要です。輪作や土壌改善を積極的に取り入れ、連作障害を未然に防ぎ、安定した収穫を目指しましょう。
家庭菜園 土 再利用のポイントと注意点
家庭菜園で使用した土は、工夫次第で繰り返し再利用することが可能です。しかし、単純に土を再利用するだけでは、作物の生育が悪くなったり病害虫が発生したりするリスクがあります。そのため、再利用する際にはいくつかのポイントと注意点を押さえる必要があります。
再利用の基本的なポイントとして、まず前回の栽培で残った根や植物の残渣をしっかり取り除くことが挙げられます。古い植物の根や葉が土壌に残っていると、それらが病原菌や害虫の住処となり、次の栽培時にトラブルを起こす可能性があります。根や残渣は丁寧に取り除き、ふるいを使って土を細かくすることで、再利用の準備を整えましょう。
次に、土の消毒とリフレッシュを行うことが大切です。消毒には、先ほども触れた太陽熱消毒がおすすめです。夏季にビニールシートをかけて土を日光に当てることで、有害な微生物や虫の卵を減らすことができます。プランターなどの小さな容器の場合は、土をビニール袋に入れて密閉し、日当たりの良い場所で数週間放置すると同様の効果が得られます。
土壌のリフレッシュについては、古い土は養分が不足しているため、必ず堆肥や腐葉土を加えて養分補給をしましょう。例えば、1㎡あたり3〜4kgの堆肥や腐葉土を混ぜ込むことで、土の保水性や通気性が回復し、植物の成長を促します。また、古い土は酸性に傾きがちなので、苦土石灰などを適量混ぜて酸度を調整することも重要です。
注意点としては、土を再利用する回数にも限度があることを覚えておきましょう。一般的に、土の再利用は2~3回程度を目安にし、それ以降は新しい土を混ぜたり、新しく購入した土と入れ替えたりするのが望ましいです。また、連作障害が起きやすいナス科やウリ科の野菜を同じ土で繰り返し育てることは避けたほうがよいでしょう。
土の再利用は節約にもなり環境にもやさしい方法ですが、適切な処理を怠ると問題を引き起こします。これらのポイントや注意点を理解して、安全かつ効果的に再利用しましょう。
家庭菜園 土 作りで押さえるべきポイントまとめ
 土は水はけと保水性のバランスが大切
土は水はけと保水性のバランスが大切 土壌は適度なpH(弱酸性~中性)が理想的
土壌は適度なpH(弱酸性~中性)が理想的 栄養豊富で微生物が多い土ほど野菜は育つ
栄養豊富で微生物が多い土ほど野菜は育つ 土の種類は栽培環境に合わせて選ぶ
土の種類は栽培環境に合わせて選ぶ 培養土は初心者向きで手軽に使える
培養土は初心者向きで手軽に使える 赤玉土は水はけ改善に適している
赤玉土は水はけ改善に適している 腐葉土や堆肥を加えることで土質を改善する
腐葉土や堆肥を加えることで土質を改善する 土の酸性調整には苦土石灰を使う
土の酸性調整には苦土石灰を使う 石灰は苗植えの2週間前に施す
石灰は苗植えの2週間前に施す 肥料は元肥と追肥を分けて施す
肥料は元肥と追肥を分けて施す 堆肥は完熟したものを使う
堆肥は完熟したものを使う 堆肥は苗植え1ヶ月前に混ぜると良い
堆肥は苗植え1ヶ月前に混ぜると良い
 連作障害防止には輪作を行う
連作障害防止には輪作を行う 土壌消毒で害虫や病気のリスクを減らす
土壌消毒で害虫や病気のリスクを減らす 土の再利用は消毒・養分補給後に行う
土の再利用は消毒・養分補給後に行う